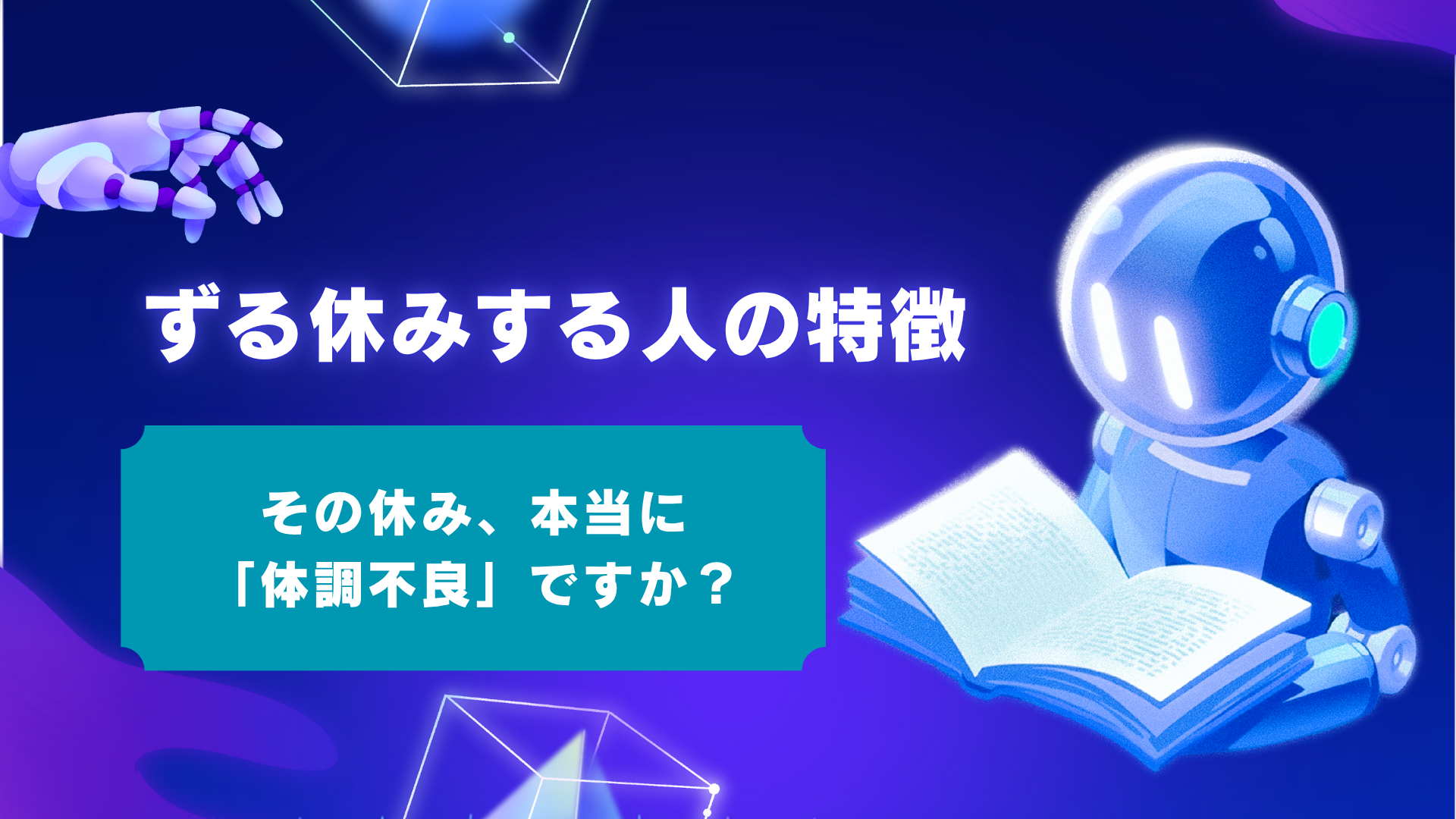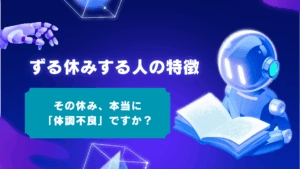「最近、特定の部下が休みがちで、もしかしてずる休みなのでは…?」
「問い詰めたいけど、パワハラだと思われたくない…」
「チームの士気にも影響が出ていて、どう対応すればいいかわからない…」
チームを率いるリーダーとして、このような悩みを抱えていませんか?部下を信じたい気持ちと、チーム全体の生産性を守らなければならない責任との間で、板挟みになっているかもしれません。
結論:部下のずる休みを疑う時、重要なのは決めつけずに対処することです。
この記事では、ずる休みする人の客観的な特徴から、その背景にある心理、さらには信頼関係を壊さない具体的な対処法まで、あなたが明日から実践できる手順を分かりやすく解説します。
この記事でわかること 3点
- ずる休みを疑うべき10の客観的な特徴とサイン
- ずる休みの背景にある4つの心理と根本原因
- パワハラにならない、上司として取るべき具体的な3ステップの対処法
ずる休み?部下に見られる10の客観的な特徴とサイン
このセクションでは、まず「ずる休みかもしれない」と感じたときに確認すべき、客観的な特徴とサインを10個リストアップします。
大切なのは、一つの特徴だけで判断せず、複数のサインが当てはまるかどうかを冷静に見極めることです。
憶測や感情で判断する前に、まずは事実を整理してみましょう。
ブログを運営していると、多くの管理職の方から「部下の休み方に悩んでいる」というご相談をいただきます。
皆さん、部下を大切に思うからこそ、どう対応すべきか深く悩まれています。
あなただけが抱えている悩みではありません。まずは状況を客観視することから始めましょう。
【曜日】月曜日や金曜日、連休の前後などに休みが集中する
最も分かりやすいサインの一つが、休む曜日に特定のパターンが見られることです。
特に、週の始まりである月曜日や、週末に繋がる金曜日に休みが集中する場合、注意が必要かもしれません。
もちろん、週末に疲れが溜まって月曜に体調を崩したり、金曜に通院したりすることは誰にでもあります。
しかし、これが数ヶ月にわたって繰り返される、あるいは繁忙期明けや連休の前後といった「休みたくなるタイミング」と面白いほど一致する場合、単なる偶然ではない可能性も考えられます。
【連絡】始業時間ギリギリか事後に、テキストメッセージだけで連絡してくる
本当に体調が悪ければ、朝起きた時点で「今日は出社できそうにない」と判断し、早めに連絡を入れるのが社会人としてのマナーです。
しかし、ずる休みを考えている場合、「休むかどうか」の葛藤から連絡が遅れがちになります。
始業時刻の直前や、場合によっては始業後に「すみません、体調不良で休みます」とチャットやメールだけで連絡が来ることが続くようであれば、その背景を少し探る必要があるかもしれません。
声色で体調を判断されたくないという心理が働いている可能性も否定できません。
【理由】「体調不良」「私用」など、休む理由がいつも曖昧で具体的でない
休む際の理由が、常に「体調不良のため」「急な私用のため」といった漠然とした言葉で片付けられていないでしょうか。
もちろん、プライバシーに関わることまで詳細に報告する必要はありません。
しかし、本当に体調が悪いのであれば、「熱が38度ありまして」「昨夜から腹痛がひどく…」といった、もう少し具体的な説明があるのが自然です。
毎回のように曖昧な理由で、こちらから質問してもはぐらかされるようなら、それは一つのサインと捉えることができます。
【症状】症状の説明が毎回変わる、または翌日にはケロリとしている
「先週は頭痛、今週は腹痛、来週はめまい…」というように、休むたびに症状がコロコロと変わるのも、一つの特徴です。
特定の持病がないにもかかわらず、都合よく様々な症状が現れるのは、少し不自然かもしれません。
また、前日に「起き上がれないほど辛い」と休んでいたにもかかわらず、翌日出社した際には驚くほど元気で、休んでいた間の業務の遅れなどにも無頓着な様子が見られる場合も、疑念を抱かせる一因となります。
【復帰後】休んだことへの罪悪感がなく、仕事の遅れを気にしない
多くの人は、急に仕事を休んでしまった場合、自分の業務をカバーしてくれた同僚や上司に対して、申し訳ない気持ちを抱くものです。
出社後には「ご迷惑をおかけしました」と謝罪し、溜まった業務をキャッチアップしようと努めるでしょう。
しかし、ずる休みをする人は、この「休んだことへの罪悪感」が希薄な傾向があります。
謝罪の言葉も形式的で、自分が休んだことでチームにどのような影響があったかをあまり気にしない素振りが見られたら、注意深く観察する必要があるかもしれません。
【SNS】休んでいるはずなのに、SNSの投稿やオンライン活動の形跡がある
これは非常に分かりやすいサインです。
「体調不良で寝込んでいる」と連絡があったにもかかわらず、その日にSNSで友人と遊んでいる写真をアップしたり、オンラインゲームにログインしていたりするケースです。
本人は軽い気持ちかもしれませんが、これを見てしまった同僚たちの不満は一気に高まります。
プライベートな活動を監視するのは問題ですが、偶然見かけてしまった場合は、客観的な事実として記録しておくべき情報と言えるでしょう。
【同僚との関係】特定の同僚が休む日に、なぜか自分も休みがちになる
職場の人間関係は、時に勤怠にも影響します。
もし、特定の仲の良い同僚が休暇を取る日に合わせて、その部下も「偶然の体調不良」で休むことが続くようであれば、示し合わせている可能性も考えられます。
もちろん、本当に偶然である可能性も否定はできません。
しかし、他の客観的なサインと合わせて、このようなパターンが見られる場合は、チーム内の人間関係やコミュニケーションに何か問題が隠れていないか、という視点で観察することも重要です。
【業務態度】重要な会議や大変な業務がある日を避けて休む傾向がある
毎月の定例会議、プロジェクトの重要なプレゼンテーション、あるいはクレーム対応など、精神的な負担が大きい業務が予定されている日を狙ったかのように休むことはないでしょうか。
誰しも、気が重い仕事からは逃げたいと思うものです。
しかし、社会人として、そしてチームの一員として、その責任を放棄するような行動が続くのであれば、それは単なる「休みがち」という言葉では片付けられない問題です。
本人の責任感や仕事へのモチベーションが低下しているサインかもしれません。
【仮病の癖】以前から軽い嘘や言い訳が多い傾向が見られる
ずる休みという行動は、その人の普段の言動と無関係ではありません。
日常の業務において、小さなミスを他人のせいにしたり、都合の悪い事実を隠すために言い訳をしたりする傾向が見られる人物は、休み方においても同様の行動をとる可能性があります。
過去の言動をさかのぼって粗探しをする必要はありませんが、普段のコミュニケーションの中で感じていた違和感が、勤怠の乱れという形で表れているのかもしれない、という視点は持っておくとよいでしょう。
【休み明け】休んだ間の業務内容や引継ぎ事項への関心が薄い
責任感のある社員であれば、休んだ翌日には「私が休んでいる間、何か問題はありませんでしたか?」「〇〇の件、どうなりましたか?」と、業務の進捗を積極的に確認するはずです。
一方で、ずる休みをする人は、自分が休んだことで発生した業務の遅延や、同僚がカバーしてくれた仕事内容への関心が薄いことがあります。
まるで他人事のように振る舞い、キャッチアップしようという意欲が見られない場合、その休みが本人にとって「仕事から逃げるための手段」になってしまっている可能性があります。
ずる休み危険度チェックリスト
▼あなたの部下の状況をチェックしてみましょう
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 1. 月曜・金曜など特定の曜日に休みが集中する | ☐ | ☐ |
| 2. 連絡が始業時間ギリギリか事後で、テキストのみ | ☐ | ☐ |
| 3. 休む理由がいつも「体調不良」など曖昧 | ☐ | ☐ |
| 4. 症状の説明が毎回変わる、または翌日は元気 | ☐ | ☐ |
| 5. 復帰後に罪悪感や仕事の遅れを気にする様子がない | ☐ | ☐ |
| 6. 休んでいる日にSNSを更新していることがある | ☐ | ☐ |
| 7. 特定の同僚が休む日に合わせて休みがち | ☐ | ☐ |
| 8. 重要な会議など、大変な業務がある日に休む | ☐ | ☐ |
| 9. 普段から軽い嘘や言い訳が多い傾向がある | ☐ | ☐ |
| 10. 休み明けに業務のキャッチアップへの関心が薄い | ☐ | ☐ |
【診断】
- 0〜2個: 現時点では過度な心配は不要かもしれません。
- 3〜5個: 注意が必要です。今後の動向を観察しましょう。
- 6個以上: ずる休みの可能性が高い状態です。次のステップに進み、慎重な対応を検討しましょう。
なぜずる休みを?責める前に理解したい4つの背景心理
部下のずる休みを疑うと、つい「けしからん」「無責任だ」と感情的になってしまいがちです。
しかし、その行動の裏には、本人も気づいていないような深刻な問題が隠れている可能性があります。
一方的に責める前に、なぜその部下はずる休みという行動を選んでしまうのか、その背景にある心理を理解しようと努めることが、根本的な問題解決への第一歩となります。
過度なストレスと燃え尽き症候群(バーンアウト)
最も多い原因の一つが、仕事による過度なストレスです。
過重な業務量、厳しい納期、達成困難なノルマなどが続くと、心身ともに疲弊しきってしまいます。
このような状態が続くと、心と体が「これ以上は無理だ」と悲鳴を上げ、強制的にシャットダウンしようとします。
ずる休みは、そのSOSサインの一つなのです。特に、真面目で責任感の強い人ほど、弱音を吐けずに一人で抱え込み、最終的に燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ってしまうケースは少なくありません。
朝、どうしても起き上がれない、会社に行こうとすると涙が出る、といった状態であれば、もはや本人の意思だけではどうにもならない段階です。
仕事へのモチベーションの低下・業務内容のミスマッチ
「この仕事、何のためにやっているんだろう…」
「自分の能力が全く活かせていない…」
仕事に対するモチベーションの低下も、ずる休みの大きな引き金となります。
自分の仕事にやりがいや意味を見出せないと、会社に行くこと自体が苦痛になります。
特に、本人の希望や適性と、実際に担当している業務内容との間に大きなミスマッチがある場合、この傾向は顕著になります。
本人は「もっとクリエイティブな仕事がしたい」と思っているのに、毎日単調なデータ入力ばかりさせられている、といった状況です。
このような状態では、仕事への情熱は失われ、休みたくなる気持ちが芽生えるのも無理はありません。
職場での人間関係の悩み
仕事内容そのものに不満はなくても、職場の人間関係が原因で出社が困難になるケースも非常に多いです。
上司からの高圧的な態度、同僚からの無視や陰口、あるいは部下との関係がうまくいかないなど、人間関係のストレスは私たちの精神を静かに、しかし確実に蝕んでいきます。
特定の人物と顔を合わせるのが苦痛で、会社に行くことを考えると動悸がする、といった状況であれば、心を守るための防衛反応として、ずる休みを選んでしまうことは十分に考えられます。
メンタルヘルスの不調のサインである可能性
見過ごしてはならないのが、うつ病や適応障害といったメンタルヘルスの不調が背景にある可能性です。
これらの不調は、単なる「気分の落ち込み」や「やる気のなさ」とは異なります。
脳の機能的な問題により、意欲や気力が湧かなくなってしまう病気です。
本人ですら「自分が怠けているだけだ」と思い込み、病気のサインに気づいていないことも少なくありません。
「休みがち」という勤怠の乱れは、メンタル不調の非常に重要な初期サインです。
もし、以前と比べて明らかに表情が暗い、口数が減った、集中力が続かないといった他の変化も見られる場合は、専門的なサポートが必要な状態かもしれません。
注意喚起
「ずる休み」は、うつ病などの精神的な不調の初期サインかもしれません。決めつける前に、産業医や専門機関への相談も視野に入れましょう。個人の判断で「怠け」と決めつけるのは非常に危険です。
参考リンク: 厚生労働省 こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
本当にずる休み?感情的になる前に確認すべき3つの判断基準
先ほど挙げた特徴にいくつか当てはまり、ずる休みの疑いが濃くなったとしても、すぐに本人を問い詰めるのは得策ではありません。
感情的な対応は、信頼関係を破壊し、事態をさらに悪化させるだけです。
ここでは、最終的に本人と対話する前に、上司として冷静に確認しておくべき3つの判断基準について解説します。
これらの基準に沿って事実を整理することで、より客観的で建設的なアプローチが可能になります。
基準1:頻度とパターン – 休みは慢性的か、特定のパターンがあるか
まずは、休みの「頻度」と「パターン」を客観的なデータとして整理しましょう。
勤怠管理システムや過去のメール・チャットの履歴を確認し、直近3ヶ月〜半年間の欠勤日をリストアップします。
- 頻度はどうか?: 月に1回程度なのか、毎週のように休んでいるのか。徐々に頻度が増えてきていないか。
- パターンはあるか?: 特定の曜日やイベント(会議、締め切りなど)と連動していないか。
この作業を行うことで、「何となく休みが多い気がする」という主観的な感覚が、「直近3ヶ月で月曜日の欠勤が6回発生している」という客観的な事実に変わります。
この事実は、後の本人との面談において、感情的な非難ではなく、具体的な状況を話し合うための重要な土台となります。
基準2:業務への影響 – その休みによって業務に具体的な支障が出ているか
次に、その部下の休みが、チームの業務にどのような具体的な影響を及ばしているかを整理します。
これは、単に「周りが迷惑している」という抽象的なレベルではなく、ビジネス上の損失やリスクとして具体的に言語化することが重要です。
- 納期の遅延: 彼/彼女が休んだことで、担当していたタスクが遅れ、プロジェクト全体のスケジュールに影響が出ていないか。
- 品質の低下: 急な休みにより、他のメンバーが不慣れな業務をカバーした結果、ミスが発生したり、成果物の品質が低下したりしていないか。
- 他のメンバーへの負荷増: 特定のメンバーが、彼の/彼女の業務を肩代わりすることが常態化し、過度な負担がかかっていないか。その結果、他のメンバーの残業時間が増えていないか。
これらの具体的な影響を明確にすることで、本人との面談の際に「君が休むと、皆が困るんだ」という感情論ではなく、「君の休みによって、〇〇という業務に遅れが生じ、チームの目標達成に影響が出ている」という事実に基づいた指導が可能になります。
基準3:コミュニケーション – 休みに関する本人との対話は十分か
最後に、自分自身の行動を振り返ってみましょう。
その部下と、休みや働き方に関するコミュニケーションをこれまで十分に取ってきたでしょうか。
- 1on1などの面談: 定期的な1on1ミーティングなどで、本人の業務状況や悩みについてヒアリングする機会はありましたか?
- 体調への配慮: 以前に休んだ際、「その後、体調は大丈夫?」といった気遣いの言葉をかけましたか?
- 期待役割の伝達: 彼/彼女がチームにおいてどのような役割を期待されているか、その重要性をきちんと伝えてきましたか?
もし、これらのコミュニケーションが不足していたのであれば、部下は「上司は自分のことを見てくれていない」と感じ、悩みを相談できずに一人で抱え込んでいるのかもしれません。
ずる休みを疑う前に、まずは上司として、コミュニケーションの機会を十分に提供できていたかを自問自答することも、公平な判断のために不可欠です。
【実践編】部下への信頼を損なわない3ステップ対処法
客観的な事実の整理と、背景にある心理への理解が深まったら、いよいよ具体的なアクションに移ります。
ここからは、部下との信頼関係を壊さず、かつ問題を解決に導くための実践的な3ステップの対処法を解説します。
最も重要なのは、「尋問」ではなく「対話」のスタンスを貫くことです。
あなたの目的は、部下を罰することではなく、彼/彼女が健全に働ける状態に戻し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることのはずです。
Step1:客観的な事実の記録と整理
面談に臨む前に、まずは準備を万全に行います。
先ほど確認した内容を、具体的な資料として手元に用意しましょう。
- 勤怠記録のコピー: 直近数ヶ月の欠勤日、遅刻・早退の記録を時系列で整理します。
- 業務影響のメモ: 具体的にどのような業務に、いつ、どのような支障が出たのかを箇条書きでメモしておきます。(例:「10/23(月)の欠勤により、A社向け提案資料の作成が遅延。火曜にBさんが3時間残業してカバー」)
- 面談のゴール設定: この面談を通じて何を目指すのかを明確にしておきます。(例:「本人の状況を正確に把握する」「今後の勤怠に関する約束を取り付ける」など)
これらの準備は、感情的な議論を避け、事実に基づいた建設的な話し合いを行うための生命線です。
準備なくして、実りある面談はありえません。
Step2:1on1でのヒアリング(声かけテンプレート付き)
準備ができたら、本人と1対1で話す場を設けます。
会議室など、他の人に話を聞かれない静かな環境を選びましょう。
面談の切り出し方は非常に重要です。「最近、休みが多いんじゃないか?」という詰問口調は絶対にNGです。
あくまで「あなたのことを心配している」というスタンスで始めるのが鉄則です。
▼【テンプレート】OKな声かけ例とNGワード
【OKな声かけ例】
上司:「〇〇さん、少し時間いいかな。最近、月曜に休むことが多いようだけど、何か大変なことはないかな? 無理していないか、ちょっと心配になって。体調面で何か気になることとか、仕事で困っていることがあれば、力になりたいと思っているんだけど。」
【ポイント】
- 「I(アイ)メッセージ」で始める: 「君は〜だ(Youメッセージ)」ではなく、「私は〜心配している(Iメッセージ)」で伝えることで、相手は防御的になりにくくなります。
- 事実を具体的に、かつ決めつけない形で提示: 「月曜に休むことが多いようだけど」と客観的な事実を述べつつ、「〜ではないか?」と疑問形で問いかけます。
- 心配している姿勢を明確に伝える: 「心配している」「力になりたい」という言葉で、対話の目的が「支援」であることを示します。
【絶対NGなワード】
- 「また休むの?」: 相手を追い詰めるだけで、何も生み出しません。
- 「本当に具合悪いの?」: 相手を嘘つきだと決めつけているのと同じです。
- 「ずる休みじゃないだろうな?」: たとえそう思っていても、口にしてはいけません。信頼関係は完全に崩壊します。
- 「みんな迷惑してるんだけど」: 「みんな」という主語の大きな言葉は、相手を孤立させ、反発を招くだけです。
ヒアリングでは、まず本人の言い分をじっくりと聞くことに徹します。
途中で話を遮ったり、反論したりせず、まずは傾聴する姿勢が大切です。
本人が話しやすいように、「そうなんだね」「何かきっかけはあったの?」と相槌や質問を投げかけ、対話を促しましょう。
Step3:具体的な改善策の合意と経過観察
本人の状況や考えを十分に聞いた上で、今後の改善策について一緒に考えていきます。
上司が一方的にルールを押し付けるのではなく、本人に「どうすれば改善できると思う?」と問いかけ、主体的に考えさせることが重要です。
- 勤怠ルールの再確認: 「体調不良で休む場合は、始業10分前までに電話で連絡する」など、具体的な連絡ルールを再確認し、合意します。
- 業務量の調整: もし業務負荷が原因であれば、「このタスクはBさんに分担しようか」など、具体的な調整案を提示します。
- 定期的な面談の設定: 「まずは2週間後にもう一度話そうか」と、定期的に状況を確認する場を設けることを約束します。
そして、合意した内容は必ず書面に残し、双方で確認しましょう。これは、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぐだけでなく、本人にとっても「約束した」という意識を高める効果があります。
【注意点】パワハラと受け取られないための法的リスクと境界線
部下への指導は、一歩間違えればパワーハラスメント(パワハラ)と受け取られかねません。
特に、ずる休みを疑うというデリケートな状況では、細心の注意が必要です。
労働施策総合推進法で定められたパワハラの3要素を常に念頭に置きましょう。
- 優越的な関係を背景とした言動(上司から部下への指導はこれに該当)
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
客観的な事実に基づかず、「やる気がないのか」などと人格を否定したり、他の社員の前で叱責したりする行為は、明らかに「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」指導と判断される可能性が高いです。
あくまで客観的な事実に基づき、個室で、相手の人格を尊重しながら対話を進めることが、法的リスクを回避する上で不可欠です。
ずる休みが起きにくいチームを作るための予防策
問題が起きてから対処することも重要ですが、より優れたリーダーは、そもそも問題が起きにくい環境を作ることに注力します。
ずる休みは、個人の問題であると同時に、チームや職場環境が抱える問題の表れでもあります。
ここでは、部下が「ずる休みをしたい」と思わないような、健全で風通しの良いチームを作るための3つの予防策をご紹介します。
これらは、ずる休みの防止だけでなく、チーム全体の生産性向上にも直結する重要な取り組みです。
日頃からのコミュニケーションを密にする(1on1の定例化)
最も効果的な予防策は、日頃からの良質なコミュニケーションに尽きます。
多くの問題は、コミュニケーション不足から生じます。
特に、1on1ミーティングの定例化は非常に有効です。
週に1回15分、あるいは隔週で30分でも構いません。
仕事の進捗確認だけでなく、部下のキャリアの悩み、プライベートの状況(話せる範囲で)、最近関心があることなど、雑談も交えながら対話する時間を定期的に確保しましょう。
このような場があることで、部下は「上司は自分のことを見てくれている」という安心感を抱き、小さな悩みや不調のサインを早期に相談しやすくなります。
問題が深刻化する前にキャッチアップできれば、ずる休みのような行動に繋がるのを未然に防ぐことができます。
業務の属人化を防ぎ、誰かが休んでもカバーできる体制を作る
「この仕事は〇〇さんしかできない」という業務の属人化は、チームにとって大きなリスクです。
その人が休んでしまうと業務が完全にストップしてしまうため、本人は「休めない」というプレッシャーを感じ、周りは「あの人が休むと困る」という不満を抱きがちです。
業務マニュアルを整備したり、複数の担当者で情報を共有したり、定期的にジョブローテーションを行ったりすることで、業務の属人化を防ぎましょう。
「誰が休んでも、チーム全体でカバーできる」という体制を構築することで、社員は安心して休暇を取得でき、急な欠勤に対するチーム内の不満も軽減されます。
これは、ずる休みだけでなく、病気や家庭の事情など、正当な理由で休む際の心理的な負担を軽くする効果もあります。
仕事の目的と役割を明確にし、本人の責任感とモチベーションを高める
仕事へのモチベーション低下はずる休みの大きな原因です。
部下が「この仕事は何の役に立っているのだろう?」と感じてしまわないよう、上司は仕事の目的や意義を繰り返し伝える責任があります。
「君が作ってくれたこの資料のおかげで、クライアントから高い評価を得られたよ」「この地味な作業が、プロジェクト全体の成功を支えているんだ」といったように、部下の仕事がチームや会社全体にどのように貢献しているのかを具体的にフィードバックしましょう。
また、各メンバーの役割と期待を明確に言語化することも重要です。
自分がチームの中でどのような役割を担い、何を期待されているのかが分かれば、自然と仕事に対する責任感が芽生え、モチベーションの維持にも繋がります。
ずる休みに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、ずる休みの対応に関して、多くの管理職が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
法的な側面も絡むため、正しい知識を持っておくことが重要です。
ずる休みを理由に解雇や減給はできますか?
1回や2回のずる休みを理由に、直ちに解雇や減給といった重い懲戒処分を下すことは、法的に見て非常に困難です。
懲戒処分には、軽いものから戒告・譴責(始末書の提出)、減給、出勤停止、そして最も重い懲戒解雇まで段階があります。
判例上、懲戒解雇が有効と認められるのは、労働者の行為が「社会通念上、雇用契約を継続できないほど悪質」な場合に限られます。
ずる休みの場合、まずは厳重注意や戒告といった形で指導を行い、それでも改善が見られず、再三の注意・指導にもかかわらず無断欠勤を繰り返すなど、悪質なケースで初めて減給や解雇が検討の対象となります。
いきなり重い処分を下すのは、権利濫用と判断されるリスクが極めて高いと認識してください。
診断書の提出を求めることはできますか?
就業規則に「病気で〇日以上休む場合は診断書の提出を求めることがある」といった規定があれば、提出を求めること自体は可能です。
ただし、診断書の提出を求める目的は、あくまで「本当に療養が必要な状態か」を確認し、適切な労務管理を行うためです。
相手を疑ってかかるような高圧的な態度で提出を強要すれば、パワハラと受け取られかねません。
また、数日の休みで毎回提出を義務付けるのは、従業員にとって過度な負担となる可能性があります。
「今回は長引いているようだから、もしよければお医者さんの診断書をもらってきてもらえるかな?」といったように、あくまで本人の健康を気遣う姿勢で依頼するのが望ましいでしょう。
他のチームメンバーへの説明はどうすればよいですか?
個人のプライバシーに最大限配慮し、憶測を呼ばないように慎重に説明する必要があります。
特定の部下が休みがちになると、他のメンバーから「また〇〇さん休みなんですか?」「不公平だ」といった不満の声が上がるかもしれません。
その際、上司として絶対にやってはいけないのが、休みがちな社員のプライベートな情報を漏らしたり、「私もずる休みだと思うんだよね」などと同調したりすることです。
これは本人の信頼を裏切るだけでなく、チーム内の不信感を煽るだけです。
他のメンバーには、「〇〇さんは現在、体調が万全ではないため、しばらく休みが多くなる可能性があります。
会社として状況は把握しており、必要なサポートを行っていきます。
業務のカバーで皆さんに負担をかける部分については、別途調整するので協力をお願いします」といったように、憶測を排除した事実と、会社としての方針を毅然とした態度で伝えましょう。
まとめ:対話を通じて、部下とチームの健全な関係を築こう
この記事では、部下のずる休みを疑った際に確認すべき客観的な特徴から、その背景にある心理、そして信頼関係を壊さないための具体的な対処法まで、ステップ・バイ・ステップで解説してきました。
重要なポイントをもう一度振り返りましょう。
- 感情的な決めつけはNG: まずは客観的な事実を整理し、冷静に状況を把握する。
- 背景を理解しようと努める: ずる休みは、ストレスやメンタル不調のSOSサインかもしれない。
- 「尋問」ではなく「対話」を: 目的は罰することではなく、問題を解決し、本人が再び活躍できるように支援すること。
- 予防が最善の策: 日頃からのコミュニケーションが、問題が起きにくい健全なチームを作る。
部下のずる休みという問題は、上司としてのあなたのマネジメント能力が試される場面でもあります。
この困難な状況を乗り越えることができれば、部下との信頼関係はより深まり、チームはさらに強く成長するはずです。
明日からできること最終チェックリスト
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ☐ | 【記録】部下の休みの日付と理由を、感情を交えずに客観的に記録する。 |
| ☐ | 【準備】もし対話が必要なら、1on1の時間を設定し、何を話すか事前に整理する。 |
| ☐ | 【対話】「心配している」という姿勢でヒアリングし、決して相手を責めない。 |
| ☐ | 【環境改善】チーム内の業務分担を見直し、特定の個人に負荷が偏っていないか確認する。 |
| ☐ | 【自己省察】信頼できる上司や同僚に、自身のマネジメントについて客観的な意見を求めてみる。 |
この記事が、あなたの悩み解決の一助となれば幸いです。一人で抱え込まず、冷静に、しかし着実に行動を起こしてみてください。
参考文献