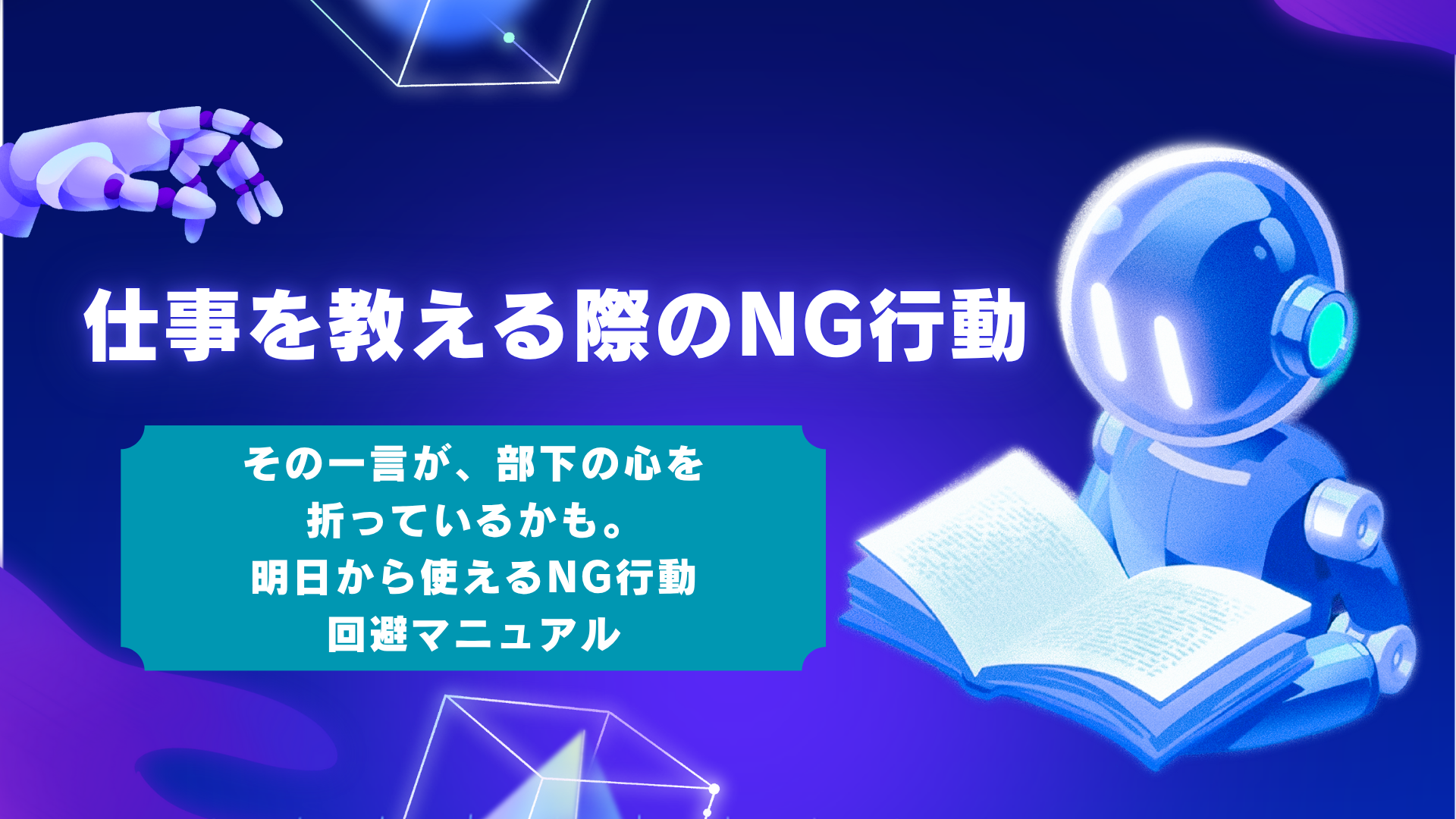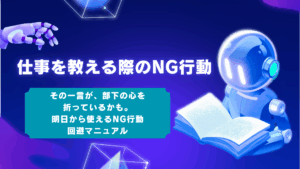結論: 仕事を教える際の失敗は、後輩の成長を妨げるだけでなく、教える側の自信も奪います。
この記事では、元ITチームリーダーの経験に基づき、絶対に避けるべき3つのNG行動と、それを乗り越え「教え上手」になるための具体的なコツを解説します。
この記事でわかること 3点
- ついやってしまいがちな、仕事を教えるときのNG行動トップ3
- NG行動を具体的なOK行動に変えるための言い換えフレーズ
- 明日から真似できる、教えるのが上手い人の共通点と心構え
前提:なぜ、仕事を教えるのはこんなにも難しいのか?
後輩や新人に仕事を教えるとき、「どうしてうまく伝わらないんだろう…」「自分の教え方が悪いのかな…」と、一人で悩みを抱え込んでいませんか?
実は、そう感じているのはあなただけではありません。
多くのリーダーや先輩社員が、同じような壁にぶつかっています。このセクションでは、まずその「難しさ」の正体を一緒に紐解いていきましょう。
あなたのせいじゃない!多くのリーダーが抱える3つの悩み
仕事を教えることの難しさは、決して個人の能力だけの問題ではありません。
それは、多くの人が共通して直面する構造的な課題なのです。
一つ目の悩みは、「自分の時間をどこまで使うべきかわからない」の原因となります。
二つ目は、「『当たり前』のレベルが相手と違う」という認識のギャップです。
あなたにとっては常識的なことでも、後輩にとっては初めて聞く専門用語や社内ルールかもしれません。
この「当たり前の基準」を無意識のうちに相手に求めてしまうと、「なんでこんなことも知らないんだ」という苛立ちにつながり、コミュニケーションの溝を深めてしまいます。
そして三つ目が、「良かれと思って言ったことが、相手を傷つけていないか不安」という心理的な負担です。
相手の成長を願うからこそのフィードバックが、意図せず相手を萎縮させてしまうこともあります。
特に最近は、ハラスメントへの意識も高まっているため、「どこまで踏み込んで指導すべきか」という線引きに悩み、結果的に当たり障りのないことしか言えなくなってしまうケースも少なくありません。
「教え方」を誰も教えてくれなかったという現実
そもそも、私たちは「仕事のやり方」は教わっても、「仕事の教え方」そのものを体系的に学ぶ機会がほとんどありません。
多くの場合、過去に自分が先輩から受けた指導法を無意識に真似たり、あるいは完全な手探り状態でOJT(On-the-Job Training)の担当になったりするのが実情ではないでしょうか。
私自身もそうでした。リーダーになった初日、上司から「じゃあ、よろしく!」と新人の担当を任されたものの、具体的な指導マニュアルがあったわけではありません。
かつて自分が経験した「見て覚えろ」というスタイルは、今の時代や職場環境に合わないことだけは分かっていました。
しかし、ではどうすれば効果的な指導ができるのか、その答えは誰も教えてくれませんでした。
この「教え方を教わらないまま、教える立場になる」という構造こそが、多くの人を悩ませる根本的な原因なのです。
ですから、もし今あなたが指導に悩んでいるとしても、それは決してあなたの能力が低いからではありません。
まずはその事実を受け入れ、ここから一緒に効果的な「教え方のスキル」を学んでいきましょう。
【結論】仕事を教えるときに絶対やってはいけないこと3選
ここからが本題です。教え方に悩む時間を最短にするために、まずは「これだけはやってはいけない」というNG行動を明確に理解しましょう。
ここでは、私がリーダー時代に多くの失敗から学んだ、特に影響の大きい3つのNG行動を、具体的な改善策(OK行動)とセットで詳しく解説します。
NG行動1:目的や背景を伝えず「作業」だけを指示する
最もやってしまいがちなのが、この「目的の欠如」です。
忙しいと、つい目の前のタスクをこなすための指示に終始してしまいますが、これは後輩のモチベーションと成長の機会を奪う、非常にもったいない指導法です。
- なぜダメなのか?:
後輩は、自分が今やっている作業が「何のために」「全体のどの部分に貢献するのか」を理解できません。その結果、ただの”作業者”になってしまい、指示されたことしかできない「指示待ち人間」になってしまいます。これでは、少し状況が変わったときに応用を利かせたり、自ら改善提案をしたりといった主体的な動きは期待できません。 - 具体的なNG例:
「鈴木さん、この顧客リストのデータ、A列とB列をVLOOKUP関数で結合して、重複を削除しておいてください。」 - OK行動への転換:
「鈴木さん、少しお願いできますか? 来週の営業戦略会議で、アプローチすべき顧客層を絞り込むために、このリストを整理したいんです。 そのために、まずA列の顧客情報とB列の昨年度の取引実績を結合して、誰がアクティブな顧客かを見える化したい。VLOOKUP関数で結合して、重複を削除してもらえますか? 最終的に、このデータを使って次のアクションプランを立てる予定です。」
いかがでしょうか。
後者の伝え方であれば、鈴木さんは「ああ、自分は今、次の営業戦略を決めるための重要なデータ整理をしているんだ」と仕事の意義を理解できます。
そうすれば、単に作業をこなすだけでなく、「もしかしたら、取引額の大きい順に並べ替えた方が会議で使いやすいかもしれない」といった、付加価値のある工夫をしてくれる可能性も高まるのです。
NG行動2:感情的・抽象的なフィードバックをする
指導する側も人間ですから、時には苛立ちや焦りを感じることもあるでしょう。
しかし、その感情的な気持ちをそのままフィードバックに乗せてしまうと、百害あって一利なしです。
また、「もっと頑張って」のような抽象的な言葉も、相手を混乱させるだけです。
- なぜダメなのか?:
感情的な叱責は、相手を萎縮させるだけです。後輩は「また怒られるかもしれない」という不安から、報告・連絡・相談を避けるようになり、結果的にミスや問題の発見が遅れるという悪循環に陥ります。また、抽象的な言葉は、具体的に何をどう改善すれば良いのかが伝わらないため、行動変容につながりません。これでは、貴重なフィードバックの機会を無駄にしてしまいます。 - 具体的なNG例:
「なんでこんな簡単なこともできないの?何度言ったら分かるんだ!」
「もっと主体的に動いてくれないと困るよ。やる気あるの?」 - OK行動への転換:
客観的な「事実」と、改善のための「具体的な行動」をセットで伝えます。
「〇〇の報告書、拝見しました。データはよくまとまっているね。ただ、結論の部分が少し分かりにくかったかな。XXという事実に対して、YYという考察が書かれているけれど、その間の論理的なつながりが見えにくいんだ。 次回は、XXという事実から、なぜYYという結論に至ったのか、その思考プロセスを1〜2行で書き加えてもらえると、もっと説得力が増すと思うよ。」
このように、人格や意欲を否定するのではなく、「行動」や「成果物」に対して、客観的な事実と改善のための具体的なリクエストを伝える。
この冷静で具体的なアプローチが、相手の素直な受け入れを促し、信頼関係の構築につながります。
「いつでも質問してね」と言いながら、質問しにくい雰囲気を作る
多くの先輩が「何か分からないことがあったら、いつでも質問してね」という言葉を口にします。
しかし、その言葉とは裏腹に、実際の行動が伴っていないケースが非常に多いのです。
これもまた、後輩の成長を阻害する大きな要因となります。
- なぜダメなのか?:
後輩は、先輩の顔色を敏感にうかがっています。「忙しそうだから後にしよう」「こんな初歩的なことを聞いたら呆れられるかも」といった過剰な遠慮から、疑問点を抱え込んだまま作業を進めてしまいます。その結果、間違った方向に進んでしまい、後で大きな手戻りが発生したり、取り返しのつかないミスにつながったりするリスクが高まります。 - 具体的なNG例:
- 後輩が話しかけてきても、パソコンの画面から一切目を離さない。
- 質問に対して、「え、そんなことも分からないの?」という表情や態度を見せる。
- 頻繁にため息をついたり、独り言で「時間がない」とつぶやいたりする。
- OK行動への転換:
「いつでも」という曖昧な言葉ではなく、質問を歓迎する具体的な仕組みを作ります。
「作業を進める上で、いくつか疑問点が出てくると思う。毎日の夕会で、今日の進捗と合わせて5分間、質問タイムを設けようか。 もちろん、緊急のことはその都度声をかけてもらって大丈夫だけど、細かい確認事項はそこにまとめて聞いてもらえると助かるな。」
「もし私が席を外している時や、すぐに返事が欲しい時は、チャットで『要確認』と付けてメンションしてくれれば、気づき次第すぐに返信するよ。」
このように、質問するための具体的な時間や方法を提示することで、後輩は「この時間なら聞いてもいいんだ」「この方法なら迷惑じゃないんだ」と安心して質問できるようになります。
教える側にとっても、業務を中断される回数が減り、集中力を維持しやすくなるというメリットがあります。
NG行動・OK行動 早わかり比較表
| NG行動 | OK行動への転換 | 後輩に与える影響(NG/OK) |
|---|---|---|
| 目的・背景を伝えない | 仕事の意義と全体像の中での位置づけを説明する | NG: 指示待ちになり、応用力が育たない OK: 主体的に考え、工夫するようになる |
| 感情的・抽象的なFB | 事実ベースで、具体的な改善アクションを伝える | NG: 萎縮してしまい、信頼関係が崩れる OK: 素直に改善点を受け入れ、成長につながる |
| 質問しにくい雰囲気 | 質問するための具体的な時間やルールを設定する | NG: 疑問を抱え込み、大きなミスにつながる OK: 安心して相談でき、問題の早期発見につながる |
一歩先へ!教えるのが上手い人が自然とやっている3つの習慣
やってはいけないNG行動を避けるだけでも、あなたの指導は大きく改善されます。
しかし、さらに一歩進んで「教えるのが上手い人」を目指すなら、彼らが無意識のうちに実践しているポジティブな習慣を取り入れてみましょう。
ここでは、後輩の成長を加速させる3つの習慣をご紹介します。
習慣1:「任せる範囲」を少しずつ広げている
教えるのが上手い人は、後輩の育成を「マラソン」のように捉えています。最初から全ての仕事を完璧にやらせようとはしません。
まずは短い距離から始めさせ、自信をつけさせながら、徐々に任せる仕事の難易度や裁量の範囲を広げていくのです。
このアプローチの鍵は、「スモールステップで成功体験を積ませる」ことにあります。
例えば、最初は資料作成の一部だけを担当させ、「この部分、すごく分かりやすくまとまっているね!」と具体的な成功体験をフィードバックする。次に、その資料のドラフト全体を任せてみる。
それができたら、今度はクライアントへの提案に同席させてみる。
このように、小さな「できた!」を積み重ねることで、後輩のモチベーションは格段に上がります。
同時に、指導する側も「ここまでは任せても大丈夫だな」という信頼感を少しずつ醸成していくことができます。
重要なのは、「失敗してもカバーできる範囲で裁量を与える」という意識です。
安全な領域の中で挑戦させることで、後輩は安心して新しいスキル習得に励むことができるのです。
習慣2:「ティーチング」と「コーチング」を使い分けている
「教える」と一言で言っても、そこには大きく分けて2つのアプローチがあります。
それが「ティーチング」と「コーチング」です。
教え上手な人は、相手の習熟度や状況に応じて、この2つを巧みに使い分けています。
- ティーチング (Teaching):
これは、知識やスキル、具体的な手順などを「教える」アプローチです。相手がまだ何も知らない、経験が浅い段階では、こちらが答えや正解を明確に提示する必要があります。「この業務は、まずAをして、次にBをして、最後にCで完了です」というように、手本を見せながら具体的に教えるのがティーチントです。 - コーチング (Coaching):
一方こちらは、相手の中にある答えや考えを「引き出す」アプローチです。ある程度業務に慣れてきた段階で、「この課題について、あなたはどう思う?」「何か他に良い方法はないかな?」といった質問を投げかけることで、相手に自ら考えさせることを促します。
新人にいきなり「君ならどうする?」と聞いても、知識がなければ答えようがありません。
逆に、ベテランにいつまでも手取り足取り教えていては、その人の成長は止まってしまいます。
相手のペースを見極め、今は答えを教えるべきか、それとも考えさせるべきか。
この判断軸を持つことが、指導の質を大きく向上させるのです。
習慣3:相手の「できたこと」を具体的に承認している
人は、自分の行動が誰かに認められたときに、喜びとやりがいを感じるものです。
教えるのが上手い人は、この「承認」の力を最大限に活用しています。
彼らは、相手が何かを達成したとき、決してそれを見過ごしません。
ここでのポイントは、「具体的に」褒めることです。
「すごいね」「よくやった」といった漠然とした言葉も悪くはありませんが、「先日のプレゼン資料、特にXXのグラフが視覚的に分かりやすくて、クライアントからの評判もすごく良かったよ。
あのグラフのおかげで契約が決まったと言っても過言じゃない。
ありがとう、本当に助かった」というように、どの行動が、どのような良い結果につながったのかを具体的に伝えることで、承認の効果は何倍にもなります。
また、承認するのは大きな成果だけではありません。
日々の業務における小さな工夫や、以前より改善されたプロセスなど、「できたこと」「成長した点」を見つけて積極的に言葉にすることが重要です。
結果だけでなく、そのプロセスを認めることで、後輩は「自分のことを見てくれている」と感じ、指導者との信頼関係がより一層深まるでしょう。
教える側の心を軽くする思考法
ここまで、効果的な指導のためのテクニックや習慣についてお話ししてきましたが、最後に、教える側であるあなた自身の心を軽くするための考え方について触れたいと思います。
どれだけ優れたスキルを身につけても、教える側が精神的に追い詰められていては、良い指導はできませんからね。
100点満点の指導を目指さない
まず、心に留めておいてほしいのは、「完璧な指導者など存在しない」ということです。
100点満点の指導を目指すあまり、自分を追い詰めてしまうのは本末転倒です。
後輩の成長は、あなたの指導だけで決まるものではありません。
本人の意欲や能力、職場環境、担当する業務との相性など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
ですから、「自分の教え方が悪いから、後輩が育たないんだ」と一人で責任を背負い込む必要はないのです。
むしろ、「一度で伝わらないのが当たり前」くらいの気持ちでいる方が、心に余裕が生まれます。
人間は忘れる生き物ですし、人によって理解のペースも異なります。
一度で伝わらなければ、伝え方を変えてもう一度試してみる。それでもダメなら、また別の方法を考える。
その試行錯誤のプロセス自体が、あなたの指導スキルを向上させてくれるのです。
【体験談】私がリーダー時代にやらかした「教え方の失敗」
偉そうなことを語っている私ですが、もちろん最初から上手く教えられたわけではありません。
むしろ、失敗の連続でした。ここで、私の恥ずかしい体験談を一つ共有させてください。
 administrator
administrator私がリーダーになりたての頃、ある若手エンジニアに新しいフレームワークの使い方を教える機会がありました。
当時の私は、「自分の知識を早くインプットさせなければ」と焦るあまり、つい自分と同じレベルの専門用語を多用して説明してしまったのです。
「ここのAPIを叩いて、返ってきたJSONをパースして…」といった具合に。
説明を終えた後、私は「何か質問は?」と聞きましたが、彼は「…大丈夫です」と答えるだけでした。
しかし、後日彼が書いたコードを見てみると、全く理解できていないことが明らかでした。
彼は、私の説明についていけず、しかし「こんなことも分からないのか」と思われるのが怖くて、質問できなかったのです。
私はこの時、痛感しました。教えるとは、自分の知識を披露することではない。
相手の目線まで下りて、相手が理解できる言葉で対話することなのだと。
この失敗以来、私は何かを教える前に、まず「この言葉の意味は分かりますか?」と相手の前提知識を確認するプロセスを必ず入れるようにしています。
この経験は、テクニカルライターとして複雑な技術を解説する今の仕事にも、間違いなく活きています。
自分一人で抱え込まず、周りを巻き込む
後輩や新人を育成するのは、指導担当者一人だけの仕事ではありません。
それは、チーム全体、ひいては組織全体の責任です。
もし指導に行き詰まりを感じたら、どうか一人で抱え込まず、あなたの周りにいる上司や同僚を積極的に頼ってください。
例えば、後輩が技術的な部分で伸び悩んでいるのであれば、その技術が得意な別の先輩に「少しだけアドバイスしてもらえないかな?」とお願いしてみる。
あるいは、あなたと後輩の関係性が少しギクシャクしてしまったと感じたら、上司に相談して1on1ミーティングに同席してもらい、客観的な視点から助言をもらうのも良いでしょう。
時には、指導役を一時的に交代してもらうことも有効な手段です。
あなたとは違うタイプの先輩から教わることで、後輩の新たな一面が引き出されるかもしれません。
チーム全体で新人を育てるという文化を醸成することが、結果的にあなたの負担を軽減し、より健全な育成環境を生み出すのです。
【FAQ】こんなときどうする?仕事の教え方 よくある質問
ここでは、これまでの内容ではカバーしきれなかった、より具体的なシチュエーションに関する質問にお答えします。
多くの指導者が一度は直面するであろう悩みに、具体的な解決策を提示します。
年上の部下や後輩に教えるときの注意点は?
これは非常にデリケートで、難しい問題ですよね。
年上の相手に何かを教える際に最も重要なのは、相手への敬意(リスペクト)を常に忘れないことです。
あなたの役職が上であっても、相手は人生の先輩であり、あなたにはない経験や知識を持っている可能性があります。
まずは、相手のこれまでの経験やプライドを尊重する姿勢を言葉で示しましょう。
「〇〇さん、この分野では私よりずっとお詳しいと思いますが、今回のプロジェクトの進め方について、いくつか共有させてください」といったクッション言葉を使うのが効果的です。
命令口調は絶対に避け、「〜していただけますか?」「〜という方法はいかがでしょうか?」といった依頼・提案型のコミュニケーションを心がけてください。
信頼関係を築くことができれば、年齢に関係なく、あなたの言葉に耳を傾けてくれるはずです。
リモートワークでの指導で、特に気をつけるべきことは?
リモートワーク環境下では、対面時以上に意図的なコミュニケーションの機会を増やすことが不可欠です。
オフィスにいれば自然にできていた「ちょっとした声かけ」や「雑談から生まれる相談」が期待できないため、意識的に接点を作る必要があります。
チャットでのやり取りが中心になると思いますが、テキストだけではニュアンスが伝わりにくく、誤解を生むこともあります。
少し複雑な指示やフィードバックを行う際は、迷わず短いビデオ通話を設定しましょう。
「5分だけいいですか?」と声をかけるだけで、認識のズレを大きく防ぐことができます。



私がリモートで新人を指導した際に効果的だったのが、「ペアプログラミング」でした。
これは、一人がコードを書き、もう一人がそれを見ながらリアルタイムでアドバイスするという手法です。
画面共有をしながら「ここはどうしてこう書いたの?」「こういう書き方もできるよ」と対話することで、相手の思考プロセスが手に取るように分かり、非常に効果的な指導ができました。
これはプログラミングに限りません。資料作成やデータ分析など、あらゆるPC作業に応用できるはずです。
何度教えても同じミスを繰り返す後輩には、どう接すればいい?
この状況は、教える側にとって最もストレスを感じる瞬間かもしれません。
ここで感情的になってしまうのが最悪の選択肢です(NG行動2を思い出してください)。
重要なのは、ミスの原因を一方的に決めつけるのではなく、本人と一緒に探るというスタンスです。
まずは、「なぜこのミスが起きてしまうのか、一緒に考えてみようか」と対話の場を設けます。
そして、「この作業のどの部分が難しいと感じる?」「どんな手順で進めているか、一度見せてもらえる?」といった質問を通じて、本人の認識やプロセスを言語化してもらいます。
そうすることで、「そもそも手順書のある項目を誤解していた」「特定のツールの使い方を勘違いしていた」といった、あなたが予期していなかった根本的な原因が見えてくることがあります。
ミスの表面だけを責めるのではなく、その根本原因にアプローチすることが、真の解決につながるのです。
まとめ:明日から、あなたの「教え方」が変わる
今回は、「仕事を教えるときに絶対やってはいけないこと」をテーマに、具体的なNG行動から、教え上手な人の習慣、そして教える側の心を軽くする思考法まで、幅広く解説してきました。
たくさんの情報をお伝えしましたが、すべてを一度に実践する必要はありません。
まずは、この記事で最も重要だと感じたこと一つからで結構です。
あなたの小さな行動の変化が、後輩の成長を促し、チームのパフォーマンスを向上させ、そして何より、あなた自身のリーダーとしての自信につながっていくはずです。
最後に、明日からの行動を具体的にイメージできるよう、チェックリストを用意しました。
ぜひ、日々の指導の前に一度、目を通してみてください。
「教え上手」になるための行動チェックリスト
| チェック項目 | はい / いいえ |
|---|---|
| □ 目的・背景から話すことを意識したか? | ☐ / ☐ |
| □ 感情的・抽象的ではなく、事実ベースで伝えたか? | ☐ / ☐ |
| □ 質問しやすい具体的な時間を設定したか? | ☐ / ☐ |
| □ 小さな成功体験を積ませる工夫をしたか? | ☐ / ☐ |
| □ 相手のできたことを見つけて承認したか? | ☐ / ☐ |
| □ 一人で抱え込まず、周りに相談できそうか? | ☐ / ☐ |
この記事が、あなたのリーダーとしての素晴らしい一歩を後押しできれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたの「教え方」が変わることで、あなたと後輩、そしてチームの未来が、より良いものになることを心から願っています。