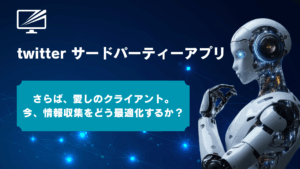残念ながら、APIの厳格化により、かつてのようなサードパーティ製Twitterクライアントアプリはほぼ全滅しました。
しかし、公式アプリの欠点を補い、効率的な情報収集を実現する代替手段は存在します。
この記事では、元・愛用者の筆者が試行錯誤の末に見つけた最適解を具体的に解説します。
この記事を読めば、あなたの情報収集効率は必ず向上します。
この記事でわかること 3 点
- サードパーティアプリが締め出された理由と現在の状況
- 今すぐ使える5つの代替案とそれぞれのメリット・デメリット
- 公式アプリのタイムラインに悩まされないための具体的な情報収集術
突然の終焉…Twitterサードパーティアプリが使えなくなった理由
多くのTwitterヘビーユーザーにとって、2023年の初頭は悪夢のような時期でした。
長年愛用してきたサードパーティ製のクライアントアプリが、ある日を境に突然タイムラインを読み込まなくなったのです。
このセクションでは、まずこの問題の背景と、なぜこのような事態に至ったのかを、技術的な詳細に立ち入りすぎず、分かりやすく解説します。
 administrator
administrator私自身、10年以上も『Tweetbot』を愛用してきました。タイムラインが汚染されず、リスト機能を駆使して効率的に情報収集する日々は、もはや仕事の一部でした。だからこそ、2023年初頭に突然アプリが使えなくなった時の衝撃と不便さは、皆さんと同じように痛感しています。まずは、なぜこんな事態になったのかを簡単に振り返ってみましょう。
2023年に何が起きた?X社(旧Twitter社)によるAPI仕様変更
結論から言うと、サードパーティアプリが使えなくなった直接的な原因は、X社(旧Twitter社)によるAPIの仕様変更です。
APIとは “Application Programming Interface” の略で、ざっくり言えば、外部のアプリがTwitterの機能やデータを利用するための「接続口」のようなものです。
これまでのTwitter社は、このAPIを比較的オープンに提供していました。
そのため、世界中の開発者が独自の思想や便利な機能を盛り込んだ、多種多様なサードパーティアプリを開発・提供できたのです。
広告が表示されない、時系列が崩れない、UIが優れているなど、公式アプリにはない魅力を持つクライアントが数多く存在し、私たちユーザーは自分の好みに合わせて選ぶことができました。
しかし、2023年1月以降、X社はこの方針を180度転換。APIへのアクセスを意図的にブロックし、その後、新しい、非常に高額な料金プランを伴うAPI v2へと移行しました。
これにより、ほとんどのサードパーティアプリ開発者は、サービス提供の継続が事実上不可能になったのです。
締め出しの主な理由:APIの有料化とデータアクセスの厳格化
では、なぜX社はこのような厳しい措置に踏み切ったのでしょうか。
公式な発表と、外部からの分析を総合すると、理由は大きく分けて2つ考えられます。
一つ目は、収益化の強化です。
X社は、プラットフォームの主な収益源である広告事業を自社のコントロール下に置きたいと考えています。
サードパーティアプリの多くは広告を表示しないため、それらのユーザーからは広告収入が得られません。
全ユーザーを公式アプリに集約させることで、広告表示の機会を最大化する狙いがあったことは間違いないでしょう。
また、新しいAPIを有料化し、企業などから直接ライセンス料を得るという新たな収益モデルへの転換も大きな目的です。
二つ目は、プラットフォームの管理と健全性の維持です。
オープンなAPIは便利な反面、悪意のある開発者によってスパムやボットのアカウントが大量に作成される温床にもなっていました。
APIへのアクセスを厳格に管理し、審査を経た開発者のみに利用を許可することで、プラットフォーム全体の健全性を向上させたいという意図もあったとされています。
「生き残り」や「復活」の可能性は限りなく低いのが現状
「では、いつかまた昔のようなアプリが復活するのでは?」と期待する声も聞こえてきそうですが、残念ながらその可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。
新しいAPIの料金体系は、個人開発者や小規模なチームが趣味や善意でアプリを維持できるレベルを遥かに超えています。
月額数万ドル(数百万円)にもなると言われる利用料を支払ってまで、無料または安価なクライアントアプリを提供するビジネスモデルは成り立たないのです。
私たちユーザーができることは、この現実を受け入れ、今ある環境の中でいかにして快適な情報収集手段を再構築するか、という点に思考を切り替えることです。
次のセクションからは、そのための具体的な代替案を詳しく見ていきましょう。
【結論】今すぐ使える!サードパーティアプリの代替案5選
サードパーティアプリが使えなくなった今、私たちは公式アプリの使い勝手に甘んじるしかないのでしょうか?答えは「いいえ」です。
かつての快適さを完全に取り戻すことは難しいかもしれませんが、工夫次第で公式アプリの欠点を補い、情報収集の効率を格段に向上させる方法は存在します。
このセクションでは、筆者が実際に試し、現在も活用している5つの具体的な代替案を紹介します。
代替案①:X Pro (旧TweetDeck) – 公式最強クライアント
まず最初に検討すべきは、公式が提供する高機能クライアント「X Pro(旧TweetDeck)」です。
元々は独立したサービスでしたが、Twitter社に買収され、現在はX Premium(有料プラン)の特典機能として提供されています。
こんな人におすすめ:PCでの作業が多く、複数のタイムラインや検索結果を一覧したいパワーユーザー。
- メリット:
- 複数のカラム(列)を自由に配置でき、タイムライン、通知、リスト、検索結果などを同時に表示可能。
- 広告が一切表示されない。
- 予約投稿や複数アカウントの管理機能も充実。
- デメリット:
- 利用にはX Premiumへの加入が必須。
- スマートフォン用の公式アプリはなく、ブラウザ経由での利用となるため操作性はいまひとつ。
かつてのTweetDeckを知るユーザーにとっては馴染み深い選択肢であり、PCでの情報収集効率を最大化したいのであれば、最も有力な候補となるでしょう。
代替案②:PCブラウザ版X + 拡張機能 – PC作業の最適解
X Premiumに課金したくない、という方に最適なのがこの方法です。
PCのWebブラウザ(Google ChromeやFirefoxなど)でXにアクセスし、拡張機能(アドオン)を組み合わせることで、表示を自分好みにカスタマイズします。
こんな人におすすめ:PCでの利用がメインで、コストをかけずに表示を最適化したい人。
- メリット:
- 広告や「おすすめユーザー」などの不要な表示を非表示にできる。
- タイムラインの表示を時系列に固定するなど、UIを細かく調整可能。
- 無料で利用できる拡張機能が多い。
- デメリット:
- Xの仕様変更で拡張機能が突然使えなくなるリスクがある。
- 導入や設定に多少の知識が必要。
具体的な拡張機能については、後のセクションで詳しく解説します。
この方法は、かつてのサードパーティアプリが持っていた「自分好みにカスタマイズする楽しさ」を少しだけ取り戻せる選択肢です。
代替案③:RSSリーダー連携 – 特定アカウントの投稿を確実に追う
これは少し上級者向けの方法ですが、特定の重要なアカウントの投稿だけは絶対に見逃したくない、というニーズに完璧に応えます。
「Nitter」のような有志によるプロキシサービスを経由して特定ユーザーのタイムラインをRSSフィードに変換し、それを「Inoreader」や「Feedly」といったRSSリーダーに登録します。
こんな人におすすめ:ジャーナリスト、研究者など、特定分野の専門家や公式発表のアカウントを確実にフォローしたい人。
- メリット:
- アルゴリズムに邪魔されず、投稿を時系列で確実に捕捉できる。
- 他のニュースソースと一元管理できる。
- Xにログインしていなくても投稿を閲覧できる。
- デメリット:
- 設定がやや煩雑で、技術的な知識を要する。
- Nitter等のサービスが不安定になることがある。
- 「いいね」やリプライなどのアクションはできない。
情報収集を「フロー」から「ストック」に変える、強力な手法です。
代替案④:MarinDeckやTwidere Xなどの派生Webクライアント
API規制後、一部の開発者がX Pro(TweetDeck)の仕組みを応用したり、Web版Xをアプリのように見せかけたりする、いわゆる「Webクライアント」を開発しています。
代表的なものに「MarinDeck」や「Twidere X」があります。
こんな人におすすめ:スマホでもカラム表示を使いたい人。TweetDeckライクなUIが好きな人。
- メリット:
- スマートフォンでカラム表示を実現できる。
- 公式アプリにはない独自のカスタマイズ機能を持つものがある。
- デメリット:
- 非公式な手法を用いているため、Xの仕様変更で突然使えなくなるリスクが最も高い。
- セキュリティ面でのリスクがゼロではない(アカウント情報の取り扱いには注意が必要)。
あくまで「現状は使える」というレベルの選択肢ですが、特定のニーズにはマッチする可能性があります。
代替案⑤:公式アプリの「リスト機能」を徹底活用する
最後に紹介するのは、最も基本的かつ確実な方法、公式アプリの「リスト機能」を使いこなすことです。
多くの人が意外と活用しきれていないこの機能を再評価することで、情報収集の質は大きく変わります。
こんな人におすすめ:すべてのユーザー。特にスマホでの利用がメインの人。
- メリット:
- 公式機能なので、サービスが停止するリスクがない。
- 作成したリストのタイムラインには広告が表示されず、時系列で表示される。
- 興味のある分野ごとにアカウントを分類し、ノイズの少ないタイムラインを作成できる。
- デメリット:
- リストの作成や管理に手間がかかる。
- メインのタイムラインの使い勝手は改善されない。
サードパーティアプリを失った今、この「リスト機能」こそが、混沌としたタイムラインから自分に必要な情報だけを効率的に得るための生命線と言っても過言ではありません。
目的別に徹底比較!あなたに最適なTwitter情報収集法は?
5つの代替案を提示しましたが、「結局、自分にはどれが合っているのか?」と迷う方も多いでしょう。
このセクションでは、あなたの目的やニーズに合わせて、どの選択肢が最適なのかを具体的に比較・解説していきます。
完璧な解決策はありませんが、複数の方法を組み合わせることで、かつての快適さに近づけるはずです。
サードパーティアプリ代替案5選 目的別比較表
| 目的・ニーズ | ◎ 最適 | ○ 適している | △ 条件付きで可 | × 不向き |
|---|---|---|---|---|
| 広告を完全に非表示にしたい | X Pro | ブラウザ拡張機能 | – | リスト機能, RSS連携, Webクライアント |
| 時系列タイムラインを維持したい | リスト機能, RSS連携 | X Pro | ブラウザ拡張機能 | Webクライアント |
| PCでの作業効率を最大化したい | X Pro | ブラウザ拡張機能 | RSS連携 | リスト機能, Webクライアント |
| スマホでの閲覧を快適にしたい | リスト機能 | Webクライアント | X Pro (ブラウザ) | ブラウザ拡張機能, RSS連携 |
| 複数アカウントを管理したい | X Pro | Webクライアント | – | リスト機能, ブラウザ拡張機能, RSS連携 |
| コストをかけたくない | リスト機能, ブラウザ拡張機能, RSS連携 | Webクライアント | – | X Pro |
| 情報を見逃したくない(確実性) | RSS連携 | リスト機能 | X Pro | ブラウザ拡張機能, Webクライアント |
とにかく広告を消したいなら:「X Pro」か「ブラウザ拡張機能」
タイムラインに頻繁に表示される広告にうんざりしているなら、選択肢は「X Pro」か「ブラウザ拡張機能」の2つに絞られます。
最も確実で安全なのは、有料の「X Pro」を利用することです。
公式機能であるため、広告は完全に排除され、今後のXの仕様変更にも対応し続けるでしょう。
複数カラム表示などの恩恵も受けられます。
一方、コストをかけたくない場合は、「ブラウザ拡張機能」が有効です。
多くの広告ブロック系拡張機能は、タイムライン上のプロモーション投稿を非表示にする機能を持っています。
ただし、これは非公式な方法であるため、X側のHTML構造の変更などで、ある日突然機能しなくなる可能性があることは常に念頭に置く必要があります。
時系列タイムラインを絶対視するなら:「リスト機能」か「RSS」
アルゴリズムによる「おすすめ」に左右されず、フォローしている(あるいは注目している)アカウントの投稿を純粋に時系列で見たい、という強いこだわりを持つ方には「リスト機能」と「RSS連携」が最適です。
公式アプリやWeb版で「リスト」を作成し、そのタイムラインを表示すれば、そこには広告も「おすすめ」も介在しません。
登録したアカウントの投稿が、投稿された順に並びます。これが最も手軽で確実な方法です。
さらに確実性を求めるなら、「RSS連携」が究極の選択肢となります。
RSSリーダーは、対象アカウントの投稿を機械的に取得・表示するだけなので、表示順が崩れることは絶対にありません。
ただし、設定の煩雑さと、利用する外部サービスの安定性が課題となります。
複数アカウントを頻繁に切り替えるなら:「X Pro」が最有力
個人用、仕事用、趣味用など、複数のアカウントを使い分けているユーザーにとって、アカウント切り替えの手間は死活問題です。
このニーズに対しては「X Pro」が圧倒的に優れています。
X Proは、異なるアカウントのタイムラインや通知を、それぞれ別のカラムとして並べて表示できます。
これにより、アプリやタブを切り替えることなく、すべてのアカウントの状況を一つの画面で把握することが可能です。
サードパーティアプリの多くが持っていた、このシームレスな複数アカウント管理機能を、公式で唯一引き継いでいるのがX Proなのです。
特定ジャンルの情報収集を極めたいなら:「リスト機能」と「RSS」の組み合わせ
Webデザイナーであるペルソナの高橋さんのように、「Webデザインの最新トレンド」「クライアントA社の関連情報」など、特定のテーマに関する情報収集を効率的に行いたい場合、「リスト機能」と「RSS連携」の組み合わせが最強のソリューションとなります。
まずは、テーマごとに関連するアカウントをまとめた「リスト」を複数作成します。
これにより、関心のある分野の情報をまとめてチェックできます。
さらに、その中でも特に重要で絶対に見逃したくない公式発表アカウントやキーパーソンについては、個別に「RSS連携」を設定します。
こうすることで、日常的な情報収集はリストで行い、重要情報の確実な捕捉はRSSで行う、という二段構えの情報収集体制を構築できるのです。
スマホでの快適さを求めるなら:「公式アプリのリスト活用」に慣れる
PCではなく、スマートフォンでの利用がメインの場合、残念ながら選択肢はかなり限られます。
現時点での最適解は「公式アプリを使いつつ、リスト機能を徹底的に活用する」ことに慣れる、という結論になります。
公式アプリのホーム画面(メインのタイムライン)は、スワイプで「おすすめ」と「フォロー中」を切り替えられますが、「フォロー中」ですら時系列が乱れることがあります。
そこで、アプリを開いたらまずリスト一覧画面に移動し、そこから見たいリストのタイムラインを閲覧する、という使い方を習慣づけるのです。
タブをピン留めする機能を使えば、アプリ起動時に特定のリストを最初に表示させることも可能です。
少しの手間はかかりますが、現状のスマホ環境では最もノイズの少ない情報収集法と言えるでしょう。
【実践レポート】私がサードパーティアプリから移行した全手順
理論だけではイメージが湧きにくいかと思いますので、このセクションでは、実際に私がサードパーティアプリ(Tweetbot)が使えなくなった後、どのようにして現在の快適な情報収集環境を再構築したのか、その具体的な手順をレポート形式で紹介します。
特にPCでの作業効率を重視する方には、参考にしていただける部分が多いはずです。
STEP1:情報収集の要「リスト」の再設計
最初に着手したのは、情報収集の土台となる「リスト」の全面的な見直しと再設計でした。
サードパーティアプリ時代は、強力なフィルタリング機能(ミュート機能)に頼りがちでしたが、それが使えない今、情報の入り口をコントロールするリストの重要性が格段に増したからです。
具体的には、以下のようなリストを作成・整理しました。
- 「Must Read」リスト:業界のキーパーソンやニュース速報など、絶対に見逃せないアカウントのみを入れた少数精鋭のリスト。
- 「Tech News」リスト:国内外のテクノロジー系メディアやブログのアカウントをまとめたリスト。
- 「Client Watch」リスト:クライアントや競合他社の動向をチェックするための非公開リスト。
- 「Friends」リスト:友人・知人との交流用リスト。
ポイントは、一つのリストに大量のアカウントを詰め込みすぎないことです。
目的別に細分化することで、その時々の気分や状況に応じてチェックする情報の種類を切り替えやすくなります。
STEP2:PCブラウザ版をアプリのように使う「PWA」設定
次に、PCのブラウザで開いたXを、まるで独立したデスクトップアプリのように使うための設定を行いました。
これはPWA (Progressive Web Apps)という技術を利用します。
Google Chromeの場合、Xのページを開いた状態で、アドレスバーの右端に表示される「インストール」アイコンをクリックするだけです。
これにより、Xが独立したウィンドウで開くようになり、タスクバーにピン留めすることも可能になります。
こうすることで、ブラウザの他のタブに埋もれることなく、Xに素早くアクセスできるようになります。地味な工夫ですが、作業効率への貢献度は非常に高いです。
STEP3:Google Chrome拡張機能「uBlock Origin」の導入と設定
広告や不要な表示を消すため、広告ブロック拡張機能の「uBlock Origin」を導入しました。
これは単なる広告ブロッカーではなく、ページの特定の要素を自分で指定して非表示にできる強力なツールです。
公式アプリへの移行後、しばらくは広告の多さや時系列表示の不安定さに悩まされました。しかし、Web版の活用やリスト機能の再設定など、試行錯誤の末に『これなら何とかやっていける』という最適解を見つけました。ここではその具体的な設定手順を紹介します。
uBlock Originをインストール後、Xのページで右クリックし、「要素をブロック」を選択します。
そして、タイムライン右側に表示される「おすすめユーザー」や「トレンド」などの不要な部分をクリックして指定し、ブロックフィルターを作成します。
これにより、タイムライン本体とナビゲーションメニューだけの、非常にスッキリとした表示を実現できました。
STEP4:RSSリーダー「Inoreader」との連携で情報収集を自動化
最後に、見逃し厳禁の情報を確実に捕捉するため、RSSリーダー「Inoreader」を導入しました。
前述の通り、有志が運営する「Nitter」のインスタンス(サーバー)を利用して、特定のXアカウントのタイムラインをRSSフィードに変換します。
例えば、Xの開発者向け公式アカウント「@XDev」をRSSで購読したい場合、「nitter.net/XDev/rss」といったURLをInoreaderに登録します。
(※nitter.netは一例であり、利用可能なインスタンスは変動します)
これにより、「XDev」アカウントが何か新しい投稿をすると、自動的にInoreaderにその内容が蓄積されていきます。
能動的にXをチェックしにいかなくても、重要な情報が向こうから届く仕組みが完成したのです。
安全性は大丈夫?非公式クライアント利用時の注意点
ここまで様々な代替案を紹介してきましたが、特に「ブラウザ拡張機能」や「派生Webクライアント」といった非公式なツールを利用する際には、セキュリティ面での注意が不可欠です。
利便性と引き換えに、リスクを負う可能性があることを理解しておく必要があります。
このセクションでは、安全にこれらのツールを利用するためのチェックポイントを解説します。
非公式サイトにXアカウント連携をするリスクとは
非公式のアプリやサービスにXアカウントとの連携を許可(認証)する場合、いくつかのリスクが伴います。
最大のリスクはアカウント乗っ取りです。
悪意のあるアプリに書き込み権限(ツイートやDM送信の権限)を与えてしまうと、あなたのアカウントから勝手にスパム投稿をされたり、フォロワーに不審なDMを送られたりする可能性があります。
また、あなたの個人情報が不正に収集されるリスクもゼロではありません。
連携を許可するということは、そのアプリがあなたのプロフィール情報やフォロー・フォロワーのリストなどにアクセスすることを許可する、ということです。信頼性の低いサービスにこれらの情報へのアクセス権を与えるのは避けるべきです。
アプリ連携時に確認すべき3つのチェックポイント
新しいツールにアカウント連携を求める画面が表示されたら、すぐに「許可」ボタンを押すのではなく、以下の3点を必ず確認する癖をつけましょう。
- 開発元の信頼性:そのツールは誰が作っているのか?公式サイトやGitHubのページなどで、開発者の情報や評判を確認しましょう。多くのユーザーから支持されている、実績のあるツールを選ぶのが基本です。
- 要求される権限の範囲:連携時に「このアプリは次のことができます」といった形で、要求される権限の一覧が表示されます。タイムラインを閲覧するだけのツールが、DMの送信やプロフィール変更の権限まで要求してきたら、それは明らかに不審です。必要最小限の権限しか要求しないツールを選びましょう。
- プライバシーポリシーの有無:信頼できるサービスであれば、収集した情報をどのように取り扱うかを定めたプライバシーポリシーを公開しているはずです。その内容に目を通し、不審な点がないか確認することも重要です。
万が一のための「連携アプリ」棚卸し手順
過去にどのようなアプリと連携したか忘れてしまった、という方も多いのではないでしょうか。
定期的に連携アプリの棚卸しを行い、現在使っていないものや、身に覚えのないアプリとの連携を解除することをおすすめします。
手順は簡単です。
- Xの設定画面から「セキュリティとアカウントアクセス」を選択します。
- 「アプリとセッション」→「連携しているアプリ」をクリックします。
- 過去に連携を許可したアプリの一覧が表示されるので、一つひとつ確認します。
- 不要なアプリや不審なアプリがあれば、それをクリックし、「アプリの許可を取り消す」を選択します。
これにより、意図しないアプリがあなたのアカウントにアクセスし続けるのを防ぐことができます。
少なくとも半年に一度は、この棚卸しを行うことを強く推奨します。
よくある質問 (FAQ)
この記事の締めくくりとして、サードパーティアプリの現状に関して、多くの人が抱くであろう疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
昔使っていたJanetterやTweetbotはもう使えませんか?
はい、残念ながらAPIを利用していた従来のネイティブアプリは、ほぼすべて利用不可能です。
Janetter, Tweetbot, Twitterrific, Echofonなど、かつて人気を博したクライアントアプリのほとんどは、2023年のAPI仕様変更以降、開発・サポートを終了しています。
これらのアプリを起動しても、タイムラインを読み込むことはできません。
有料のX Premiumに登録すればサードパーティアプリは使えますか?
いいえ、X Premiumに登録しても、サードパーティアプリが使えるようにはなりません。
X Premiumの特典は、広告の削減、長い投稿の作成、そして公式クライアントである「X Pro (TweetDeck)」の利用権などです。
サードパーティアプリ開発者向けのAPIアクセス権とは全く別のものです。
X Premiumに加入したからといって、使えなくなったアプリが復活することはありません。
今後、サードパーティアプリが復活する可能性はありますか?
限りなくゼロに近い、というのが現状での見方です。
前述の通り、X社が現在の高額なAPI料金体系を維持する限り、個人や小規模チームがサードパーティクライアントを開発・提供することはビジネス的に不可能です。
X社が方針を再び大きく転換しない限り、私たちが知っていたような多様なサードパーティアプリのエコシステムが復活する可能性は極めて低いでしょう。
まとめ:さようならサードパーティアプリ。これからの情報収集戦略
本記事では、Twitterサードパーティアプリがなぜ使えなくなったのかという背景から、現状で取りうる5つの具体的な代替案、そしてそれらを目的別に比較・選択するための指針まで、詳しく解説してきました。
サードパーティアプリが乱立していた、あの自由な時代に戻ることはもうないでしょう。
しかし、嘆いてばかりではいられません。
紹介した方法を組み合わせることで、公式アプリの欠点を補い、自分だけの快適な情報収集環境を再構築することは十分に可能です。
- PCでの作業効率を最優先したい → まずは「X Pro」を検討。コストをかけたくないなら「ブラウザ拡張機能」。
- 時系列でクリーンなTLが見たい → 「リスト機能」の徹底活用から始める。
- スマホでの閲覧がメイン → 「リスト機能」を使いこなすことに慣れる。タブのピン留めも活用する。
- 特定ジャンルの情報を漏れなく追いたい → 「リスト機能」と「RSS連携」を組み合わせる。
- セキュリティが何よりも大事 → 「リスト機能」や「X Pro」など公式機能の範囲で工夫する。
この記事で紹介した方法を参考に、ぜひご自身の使い方に合った新しい情報収集の形を見つけてください。
まずはPCブラウザのお気に入り(ブックマーク)に、特定のリストページのURLを直接登録することから始めるのがおすすめです。